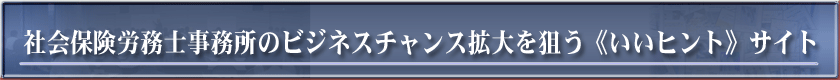|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
�� �ĶȤǤ��쥳��ƥ��Ǥ��졢���Ź٤Ǥ���ζȶ�̳�Ǥ��졢�����ǤϾ��ʤ䥵���ӥ����в��Ȥ��Ƥ����⤬“��”����ޤ��������Ƥ����“������”�Ǥ���������“����”�ˤϡ��ɤ����Ƥ�“�����ʧ���ʵҡ�”¦�������ʤ䥵���ӥ����ԡ�����ˤ��Ф���ͥ�̤�Ω�������Ǥ���
�� ���̤ξ�������ʤ顢�ܵҤ�ͥ�̤�Ω����Ƥ⡢����Ф����OK�����Τ�ޤ����ܵҤ�“��Ƴ”����Ω���Ȥ�ζȤǤϡ�����κݤ˸ܵҤ�“ͥ��”��Ω�����ȡ����θ�����ˤ��ˤ����ʤ�Ǥ��礦���ؤ������Ω�������˱ĶȤϤ������ʤ��٤Ȥ���������¿���Τ����Τ�ޤ���
�� �Ȥ��������ºݤ˱ĶȤƤ���Ĥ��Ϥʤ��Ȥ⡢���Ĥδ֤ˤ�“��Ϳ��”��ͥ�̤�Ω����ơ�̵��������դ����뤳�Ȥ�����ΤǤϤʤ��Ǥ��礦�����¤ϡ������“����”���褹��“����”�Τ褦�ʤ�Τ����¤ϡ�����Ū��“�ĶȥΥ��ϥ�”����˱���Ƥ���ΤǤ���
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
�ڣ����� �ʤ�����“�ߤ�����”����ˤ��Τ��� |
| |
|
|
| |
|
|
�� “���䤫����”�ǤϤ���ޤ�������“�ߤ�����”�äƤߤ��Ȥ��ޤ�������ʿ���Ǥ⡢“�ߤ�����”���ˤ��Ǥ��礦�����������衢���ι٤�“���ĤΤ�ΤΤ֤Ĥ���礤”�Ǥ����顢���Ѥ�ȿ���Ѥδط��ǡ����ˤ�“�ߤ�����”�ˤ⡢Ʊ������å����ݤ��äƤ���Ϥ��Ǥ�������ʤΤˡ�����ͪ���Ȥ��Ƥ��ꡢ“�ߤ�����”�϶줷��ΤǤ�
�� ���Ѥ�ȿ���Ѥϡ��ޤ���“�����δط�”�����Τ�ޤ���“�ɤ����Ϥ��ä�뤫”�ǡ����αƶ����礭���ۤʤ�ޤ���Ʊ������“ɨ”���ǤĤʤ顢ξ���Ȥ�“�ˤ�”�Ǥ��礦���ط���“����”�Ǥ���Ȥ��Ƥ⡢���κ��Ѥ�ȿ���Ѥ�“�ɤ�”�˲ä�뤫�ǡ�“�����”���뤤��“����”���礭���㤦�ΤǤ���
�� �ä�“�ܵһ�Ƴ��”�Υӥ��ͥ��˼���Ȥ�ݤˤϡ�����“�ݥ�����˥�”�˽�ʬ��θ���ʤ���С����Ф���“����”�����ä�“�����”����餦��̤˴٤��ǰ�������ʤ�ޤ���
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
�ڣ����� �ĶȤ�“���鷺����”�ϼҲ���Թ� |
| |
|
|
| |
|
|
�� �ĶȤϡ��ޤ��ˤ���“����”�ʤΤ�“���Ѥ�ȿ���Ѥαƶ����㤦”ŵ��Ū�ʳ�ư�ΰ�Ĥ����Τ�ޤ����Ȥ��С��ܵҤΤ����פ�“�������”��²�����Ƥ��Ƥ���Τˡ����μ�ݤ���ơ���Ϳ�褬�ؼ�ʬ�Τ郎�ޤޤ��̤�٤ȴ��㤤���뤳�Ȥ�����ޤ���
�� ���뤤�ϸ�����Τ����פ�������Ū�ʲ��ʤ�ͭ���ղò�����ƤƤ���Τˡ������褫��“�����Ķȼ�”���ܤ�뤳�Ȥ⤢��Ǥ��礦�������Ʋ���ꡢ�����“�ط���”����ǡ�“����αĶȤλ�”��������졢����������ˡ��Ķȳ�ư��“���鷺����”���������������Ȥ����顢����ϼҲ���Թ����Ȥ������ΤǤ���
�� �ʤ�“�Ҳ���Թ�”���ȿ����ޤ��ȡ�����ϴ�ȷбĤ��Բķ��“����”��“��ǽ”����Ļζȥ����ӥ����������ɬ�פȤ����Ȥ�“Ŭ�ڤ˹Ԥ��Ϥ�”�����뤫��Ǥ����ζȤ�Ư��������顢��Ȥ�“��ñ�˲��Ǥ������”�Ǥ����⡢���֤��ʤ���Фʤ�ʤ��ʤ�ΤǤ���
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
�ڣ����� ���ȼԤǤ���бļԤ�“�бIJ���”���Τ餷��롪 |
| |
|
|
| |
|
|
�� �����“�бļԤ���Ǥ”���ȸ��äƤ��ޤ��Τϴ�ñ�Ǥ�������Ȥ�“Ĺ”��“�бļ�”�ȸƤ֤Τϡ������ϤȤ⤫�������¤ˤ����꤫���Τ�ʤ��ΤǤ���
�� ������бļԤ�“����Ĺ”�Ǥ��ꡢ��ʬ�λ��Ȥˤ����̤��Ƥ��ޤ�����“�б�”�˴ؤ��Ƥϡ������ռ��⸫����“���ʤ�”�Τ����̤ʤΤǤ�������ϡ�����Ĺ��“����”����ǤϤ���ޤ���“�б�����”��“��”���顢��Ȥ��Ƴ���Ȥ��ơ���ã�μҲ�����ä��褿����Ǥ��礦��������б����ϻȤ��������“���������Ω�ĥΥ��ϥ�”�ʤΤǤ�����“����”�ˤȤäƤ�“����Ū”�ʤ�Τǡ�����Ĺ��“������”����ˤϡ�����ʤ�ι��פȻ��֤�ɬ�פʤΤǤ���
�� ��ߤβ��ͤ��Τ�ʤ��ͤˡ���ߤ��ꤲ���“�Ф��ꤲ��줿”�ȴ��㤤����ȸ����ޤ���“�бĤθ����䵻ǽ”�⡢���β��ͤ��Τ�ʤ��ͤˡ����Τޤ�“�֤Ĥ���”�ʤ顢���⤵�줿�ȴ��㤤���Ƥ��ޤ������Τ�ޤ������顢���⤵�줿�ȴ��㤤����бļԤ��������˸����äơؤ��ʤ��ϻ��Ȥ��Τ�ʤ�����ʤ����٤ʤɤȡ�����㤤��“ȿ��”�Ƥ��ޤ��Τ��Ȥ�ͤ�����ΤǤ���
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
�ڣ����� ��ʬ�ζ��ߤ�����“��”��ʬ�ˤ֤Ĥ���…�����줬�ĶȤδ��ܷ� |
| |
|
|
| |
|
|
�� �Ҳ����Τ�������ʤ�˰���������ή��Ƥ��������ˤϡ�“���Ȥ�ʤ���гμ¤����̤��Ф�”�ȸ������ΤǤ��礦�������䡢����˸����ʤ顢“����Ĺ”��“�бĸ���”��“��������”���ʤ���С���Ȥ��⳰����“����̹���”����������ˤʤ�ޤ�������¿���δ�Ȥ�“�бĸ���”�ˤ��“���ȥ���ȥ�����”���礫���ʤ��ΤǤ���
�� ���δ�����Ω�Ĥʤ顢����Ϥޤ��ˡ�“�бļ������������ʬ������”�ζ��������������س��������٤������ȸ�����Ϥ��Ǥ����Ȥ���������Ƭ�˿����ޤ����褦�ˡ��ζ����������Ȥ��Ф���“�Ѷ�Ū��Ư������”��Ԥ��ȡ������“�Ķ�”����ª����졢“��”��“�ߤ�����”�δط����褷�Ƥ��ޤ�����⡢�Τ��ˤ���ΤǤ���
�� ���ʤɿ���夲��տޤ�ʤ���������“�ߤ�����”��ȷбļԤ�“̵�ռ�”�˷���õ�������Ƥ��ޤ������Τ�ޤ��ۤȤ�ɤηбļԤϡ��Ķȡʻ��ȡˤδ��ܤ�“��ʬ�ζ��ߤ�������������ʬ�ˤ֤Ĥ���”���Ȥˤ�����ΤäƤ��뤫��Ǥ���
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
�ڣ����� ���Ȥ����դʷбļԤ��бĤ���Ȥ����ط� |
| |
|
|
| |
|
|
�� ���Ȥ��С�“�Ķ�”���Ф�Ĺ����“����Ĺ”�ϡ��бĻٱ���Ƥ˺ݤ��ظ��̤ϽФ�Τ����٤ȡ�����夲�ޤ������뤤�ϡ�����ϡؤ���ʤ����Ѥ��ݤ���Τ��٤Ȥ����������Τ�ޤ����ˤϡؤɤ��ޤǸ��Ȥ��Ƥ����Τ��٤Ȥ����������Τ褦�����Ф����Ȥ⤢�����ޤ���
�� “�б�”�˴���ʤ�����Ĺ�ϡ����Ф��С�����“�����и���”��“���ȡʽ����ˤ�̵ͭ”�꤫�����ơ������Ԥ�“�”����������ޤ���������������ʤ�Υ��ϥ���“���̤��ݾ�”���뤳�ȤϤǤ��ޤ���“���٤�Ķ��������”�ϡ�ʸ���Ҳ�ˤ���Ŭ�ڤǤ���
�� ����ɤ����������̤�“�����и��̡ʤ��Ф����¡�”���ٳ��뤷�ơ�¾�Ԥα������Ԥ���ΤǤϤʤ�“��������”��ʤ��ʤ��ʤ顢����“�бij�”�ʤɤ������ޤ���“�����и��̴���”��“�������ϲ���ռ�”����¿���δ�Ȥ�“��ä�˭���ˤʤ뤿��ηбļ�ˡ”���³����Ƥ��������װ������Τ�ʤ��ΤǤ���
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
�ڣ����� �ܵҤ�“�Ť�”���Ĺ���ƤϤ����ʤ��� |
| |
|
|
| |
|
|
�� ���Τ��ả��“�����и��̴���”��“�������ϲ���ռ�”�Ȥ�����Ĥ��ɤ�“����”����“���ߤʥ��ץ�����”��������ޤ��������ơ����줳����“�ζȤαĶȤ餷���ʤ��Ķ�ˡ”��������ư�ʤΤǤ���
�� �����“�����”�Ǹ����ȡ����ǤϤʤ�“���ʿ”��“�ߤ�����”�����Ƥ�褦�ʹ��Ǥ������ʿ�����Ƥ�ʤ顢����Ϥޤ���“������”�Ǥ��ꡢ����礤�ˤϤʤ�ޤ�������“�ߤ�����”�Ф���ǤϤʤ���������“�����ơ�”��Ф��ƹԤ����Ȥ��ǽ�ʤΤǤ���
�� ��ƶ�̳�ϡ��������ͭ���Ǥ��������“̵�������ӥ�”�ǿ���ط�����Ȥ���ȯ�ۤ�ή�Ԥ��ޤ��������ζȤΤ褦�ʸ����ӥ��ͥ����Ĥޤ�桼��������ñ�ˤ�����Ǥ��ʤ���̳���Ǥϡ�“̵��”��“����”�ǤϤʤ����ܵҤ�“�Ť�”���Ĺ���Ƥ��ޤ�����Ǥ���
�� �������“̵�������ӥ�”�ƤϤ����ʤ��ȤϿ����ޤ���“�Ť��ʤ�”��ˤϡ����ˤ�“̵�������ӥ�”��ɬ�פǤ��ꡢ����Ū���ȸ����뤫��Ǥ���
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
�ڣ����� ���ʿ�����Ƥ�“������”�Τ褦�ʱĶȤȤ�…�� |
| |
|
|
| |
|
|
�� �Ǥϡ����ʿ�����Ƥ�“������”�Τ褦�ʱĶȤȤϡ��ɤΤ褦�ʤ�ΤʤΤǤ��礦��������ϡ��ޤ��˻���Ĺ��“�Τ�”�٤��ʤΤˡ��ޤ�“�Τ�ʤ�”���Ȥ�ռ��������ܵҤ�“������”����ˤ��ʤ��顢ͭ���ʥ��ݡ��Ȥ��³���뤿���“�ܵҴѻ�”��³���뤳�Ȥ�¾�ʤ�ޤ���
�� �����ơ������“�������賫��”��“����ƥ��ץ�����”��“������������”��“����³�ط��η���”��“���ط��ο�������ɲ���ơ�”�Σ��ĤΥ��ƥå��˱��Ѥ���ȡ�“�����ƤΤ褦�ʱĶȳ�ư”���ưפˤʤ�Ϥ��ʤΤǤ���
�� �����ơ����ΰ�İ�Ĥ����Τ�“��ư�ؿ�”�䡢ɬ�פʤ��“��ư�Ѥν��ġ���”����Ĥʤ�С����γ�ư��“����”�����ǤϤʤ�“��Ψ”��������ƹԤ��Ϥ��Ǥ���
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
�ڣ����� �����“�ĶȤηɱ�”��“����”���Ѥ��䤹���� |
| |
|
|
| |
|
�� |
�� �ζȳ��Ǥϡ��ޤ��ޤ�“�Ķ�”��ɱ����������ʤ�����ޤ��ĶȤʤɤ������ʤ�����“���”��Ȥä��Τ��Ȥ���С��Τ��ˤ����“�����ʷ���”���Ȥ������ΤǤ��礦�����������Τ褦��“ȯŸ�ؤ�ή�줬�����ˤ����ʤä������Ϻ�Ū�Ķ���”�Ǥϡ�“�ĶȤηɱ�”�ϡ��ष��“����”�ˤ�ʤ�䤹���ΤǤ���
�� �ʤ��ʤ顢�Ķ�“���”Ū���á��Ĥޤꡢ��ˤ���Ŧ�����褦��“�����и���”��“���Ȥ���«”�˻�������С�“���”�����̤������Ȥळ�Ȥ���“�Ķȷɱ��”�ϡ������̣��“���Ѥ���䤹��”¸�ߤˤʤ꤫�ͤʤ�����Ǥ���“���”�ϡ�ƨ������“»”�ʤΤǤ�������������줿�顢�ष��“��꤬�Ϥ��ʤ�”�������ݤ��ʤ��顢������Ω���ʤ���Фʤ�ޤ���
�� “�ߤ�����”�Ϸ��˼夯�Ƥ⡢“���ʿ”�ʤ�С���������ߤ�뤳�Ȥ���ǽ�Ǥ���
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
�ڣ����� ���ȼԤ��ͤ���“�Ķ�”������ʳ�“����”�ĶȤΥ����� |
| |
|
|
| |
|
|
�� �����“���ʿ��”�Ķȼ�ˡ��“�������Ķ�ˡ”�Ȥ��ơ���Ĥιֺ��ˤޤȤ�ޤ���������ʤ������Ǥ����顢���դ���ɥޡ����ƥ��β�β���γ����ˤ�̵�������ۤ����Ƥ��������Ƥ��ޤ��������¿��������������“����Ĺ�ηбĤ���”�����ˤ���뤳�Ȥ��äƤ��ޤ���
�� �����طʤˤϡ��ζȻ��Ȥ���ä�“��Ψ”�褯���פ�夲�ơ���ä�“;͵”�Τ����ư��Ÿ������뤳�Ȥؤδꤤ������ޤ���������ʾ�ˡ��ζȤ��ηä�“�ȶ������˷б�Ū�˼���Ȥॻ��”������ȷбļԤ˹����뤳�Ȥν��������뤫��Ǥ���
�� �����ɤΤ褦��“�б�”��ɬ�פʤΤ��ˤĤ��Ƥϡ����ιֺ¤Ǥϸ��ڤ��Ƥ��ޤ����ޤ��ϡ���������“���������˻���”�������Ȥ�Ĺ������ȷбļԤ˰�̣�Τ������������Ȥ������顢������Ÿ�����Ϥޤ�Τ��ȹͤ��Ƥ��ޤ���
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
 |